複眼の偏光視
光には横波の性質があり、太陽光はあらゆる振動面の光を含んでいますが、それが物にあたって反射した光は、ある限られた振動面をもつ光になります。このように振動面が決まっている光を偏光といいます。水面がギラギラ光って見えるのも偏光の関係です。
人間には光の振動面を見分ける能力がないので、どの光も同じように見えますが、昆虫の複眼では、特定の偏光方向に敏感な視細胞が色々な方位に規則正しく並んでいるため、偏光を見分けることができます。
ミツバチの複眼には、背側に特殊な個眼が集まった部分があります。水平な所に止まっている場合に空を見上げている部分で、ここの個眼は偏光に特に感度が高く、太陽が地平線近くにある時の青空の偏光パターンに、ほぼ対応した配列になっているようで、ミツバチが水平な所に止まって、空が一番明るく見えるように体の向きを決めたとすると、体軸は太陽子午線と平行になり、太陽を見なくても太陽の方向を知ることができるそうです。
昆虫の帰巣の仕組み
昼間活動する昆虫が、巣から出て巣へ戻るためには、自分のいる位置を巣から見てどの方角でどれくらい離れているかを知っていなければなりません。そのためには一日の時刻を知り、その時刻の太陽の位置を知って、さらにどの方角にどれだけ移動したかを方位ベクトルとして積算できている必要があります。
太陽が見えている場合は、その位置を知ることは簡単ですが、太陽が見えてない場合でも、昆虫は偏光を利用して太陽の位置を知ることができます。
また、どれだけ移動したかは、複眼の網膜に映る像の流れをもとに、オプティカルフロー量として認識できているからだと考えられているようです。
単眼の働き
多くの昆虫は、一対の複眼とは別に、2~3個の小さい単眼をもっています。昆虫の単眼は、角膜レンズと通常数百から千個程度の視細胞の網膜からなるレンズ眼で、人間の目に似ていますが、レンズは網膜に焦点を結ばず、明暗しか検知できないようですが、その代わりに光強度の変化には感度良く検知できる構造であり、信号伝達速度もきわめて速いそうです。
この3つの単眼の明暗変化の組み合わせにより、体の縦揺れ、横揺れ、それに回転といった飛翔姿勢を制御していることが確認されていて、薄暗い木々の間をぶつからないよう通り抜け、すばやく姿勢を立て直すことができるのは、単眼のお陰だということです。
昆虫の単眼3個による姿勢制御の仕組みをまねて、3個の光センサーを備えた飛行安定装置がラジコン飛行機の制御に活用されていて、特にきりもみ落下の状態から姿勢を立て直すのに威力を発揮しているようです。
不完全変態するトンボやセミなどの昆虫は、幼虫時代から複眼が形成されてきますが、完全変態するチョウの幼虫には複眼はなく、口の両側にある触角の少し上に6個ずつの小さな点状の単眼をもっています。この単眼は成虫の単眼とは異なり、複眼の一個一個に相当するようです。
アゲハチョウの尾端光受容器
アゲハチョウは、前脚で葉の味を確かめたうえで、腹を曲げて産卵をします。産卵のため、産卵管の両脇に、紫外線から青にかけての波長範囲でよく反応する光受容器があります。この光受容器を使って、産卵管が十分に突き出されていることを確認したうえで、産卵管が何かに触れると卵を産む仕組みになっていて、光受容器が壊されてしまうと、産卵管が出たかどうかわからなくなり、うまく産卵できなくなってしまうようです。
メスだけでなくオスにもあります。オスの場合は、交尾のときにメスの交尾器を支えるバルバという構造を開いたところにあり、交尾がうまくできるとこの受容器への光が閉ざされることで、確認ができているようです。
視覚能力について調べてみました(3)昆虫の特別な視覚能力
視覚能力について調べてみました(2)色覚と紫外光、夜行性動物
色覚
人間の目の網膜にある視細胞には、3種類の錐体と1種類の桿体があります。3種類の錐体は長波長(赤)、中波長(緑)、短波長(青)に感度をもっています。しかし網膜には3種類が均等に配列している訳でもなく、感度レベルも異なるようです。
色覚は物にとって絶対のものでなく、人間の場合には人間の3種類の錐体で感知したレベルに合わせた信号を脳が処理して、さまざまな色として認識しているものです。黄色の単独光と赤と緑を組み合わせた光が識別できないばかりか、一番波長の短い紫光と、それより波長の長い青と赤との組み合わせ光が同じだと認識してしまいます。
また、太陽光あるいは白色下で赤く見えている物は、赤色が反射してくるのを感知しているからで、暗い部屋で赤色光を当てればそのまま赤く見えますが、緑色光を当てれば吸収されて黒くなってしまうため、色がわからなくなってしまいます。
紫外光が見える動物
恐竜全盛時代の哺乳類は小さな夜行性動物で、魚類から爬虫類や鳥類が4種類の色覚をもつのに対して、哺乳類は色覚を退化させる代わりに暗いところでも見える能力を高めたと言われており、2種類の錐体しかもっていません。
しかし、人間に近いチンパンジーやオランウータンなどは、そのうちの1種類を変化させて赤と緑の色覚を獲得し直したことで3種類もっていますが、ある比率で赤と緑の色覚異常が発生したり、赤の感覚が人によって異なったりするようです。
魚類から爬虫類や鳥類も、全てが4種類の色覚能力をもっている訳ではないようですが、鳥類などは紫外線を識別できており、紫外、青、緑、赤の色覚をもっていると言われています。
昆虫もまた、紫外を含む4種類の色覚をもっているものが多くありますが、ミツバチは紫外、青、緑の3種類の色覚のようです。
鳥や昆虫にとっては、雌雄の判別や植物の花を認識する上で、紫外光による色覚が重要で、人間にとっては見えない形状も紫外光で見ることで判別できているということです。
紫外光の色覚があれば、人間にとって同じに認識してしまう紫の単独光と青と赤との組み合わせ光とでは、まったく異なるものとして認識できるでしょう。
視感度
明るい所から暗い所へ入ったり、突然明りが消えたりすると、一瞬真っ暗で何も見えなくなりますが、やがて目が慣れてくると見えてくるようになります。
明るい所では錐体により色覚を伴って物を見ますが、暗い所では色覚には関与しない代わりに感度の高い桿体により見るように変わるからで、従って色ははっきりとしません。
夜行性動物にとっては、色覚よりも暗い中でもよく見える方が大事であり、錐体を減らして桿体を充実させているようです。
桿体は色を認識することができませんが、色に対する感度は異なりますので、色による明暗の差が生じます。青の方が赤より明るく見えるといった、モノクロトーンで見ることができます。
夜行性動物の輝板 (タペタム)
猫が暗闇でもよく見えるのは、人間と比べて錐体が約1/6しかない代わりに桿体が6倍以上もあるだけでなく、猫の網膜の下には夜行性動物に備わっている光を反射させる輝板という層があり、網膜をいったん通過した光が輝板で反射して、再び網膜の視細胞を刺激するからです。
この輝板は、人間には見えない波長の短い光を波長の長い可視光に変え、蛍光を発するため、暗い所で夜行性動物に照明を当てたとき、眼が光って見えます。この現象はシカなどの野生動物でも同様であり、ライトで照らして光って見えた眼の数で個体数を割り出す「ライトセンサス」に利用されています。
(付記)
夜間に目が良く見えない夜盲症のことを鳥目といいますが、ニワトリは夜良く見えてないようでも、フクロウのように夜行性の鳥もおり、渡りをする小鳥などは猛禽類をさけて夜移動しています。鳥の目が必ずしも夜良く見えない訳ではありません。
人間の夜盲症はビタミンAの不足によって起こると言われていますが、暗い所で見るための桿体が機能するために必要なロドプシンという物質が作られるためには、ビタミンAが必要だからです。
視覚能力について調べてみました(1)物を見るということと視力
目の検査といえば、普通は視力検査によって、どれだけ細かいものまで見えるかを調べます。また、色が識別できるかどうかを調べることもあります。しかし、視覚能力はこれだけではありません。視野が広いか、暗いところでもよく見えるか、速く動くものに追随できるかといった能力も大事です。
動物は、それぞれの生態様式に合わせて、視覚能力を身につけていることを、人間の視覚能力と比較しながら調べてみました。
物を見るということ
物に光が当たると一部は吸収され、残りが反射されますが、この反射されてくる光が物を見ている動物の目に届きます。目に届いた光に感度をもつ光受容器と、その光受容器からの信号を処理する脳の画像処理システムが、動物の進化過程によって異なったものと
乙女高原フォーラムに参加してきました
乙女高原フォーラム
2011年2月6日、山梨市民会館で開催された第10回乙女高原フォーラム「シカ・人・乙女高原の今と未来」に参加してきました。3年続けて「シカ」がフォーラムのテーマです。
乙女高原ファンクラブの活動
開会の挨拶が終わると、初めに乙女高原ファンクラブの活動報告があり、続けて乙女高原で行われているシカ柵のモニタリング調査の中間報告がありました。
(社)関東建設交際会による弘済会「関東・水と緑のネットワーク拠点選」支援事業としての助成金により、昨年5月9日にボランティアの協力で、草原2か所と湿地に1か所シカ柵を設置し、その後ほぼ1週間に1回のペースでシカ柵周囲と内側の状況を観測した。
柵の外側では、今年6月5日にタムラソウとシシウドの葉が、7月10日にはタムラソウとハンゴンソウの葉が採食されているのが認められ、内側より草丈が低いことが観察された。一方、内側では、7月25日にミズチドリが4年ぶりに開花しているのが確認されたことなどが報告されました。
山梨県内各地の活動事例
次に、山梨県内各地でシカ問題に取り組んでいるグループの事例が報告されました。
● 南アルプス市の櫛形山アヤメ保全対策
地元の巨摩高校自然科学部が過去に行った調査結果で、アヤメ平と裸山の総株数約2900万本、花数約320万個と推定されたアヤメが、年々減少してきているという指摘もあったが、平成18年に開花数が激減し、平成19年にはほとんど咲かなくなってしまった。
いろんな原因が考えられたが、シカの食害といった外的要因を除去してみるために、アヤメ平に4か所、裸山に3か所、ネットを設置したところ、3年目の昨年、平成22年に、ネットの中ではアヤメが数10個咲いているのが確認された。
他の要因も考えられるので、植生の復元のため、モニタリングを続けながら保全対策を検討し、櫛形山の自然の魅力を地域力で高めていきたいとの発表でした。
● 八ヶ岳自然クラブのシカグループのライトセンサス活動
八ヶ岳南麓のシカの生息状況を把握するため、高原道路の車中より、八ヶ岳牧場を投光機により、毎年、12月から翌年3月まで、月3回程度、期間中10回以上の観察を行ってきた。
ニホンジカは増えていること、群れが大きくなっていること、12月~1月は特に多く出現することがわかっており、幼樹の食害・樹皮はがし、牧草の減収、庭や菜園の食害、さらには電車や自動車との衝突といった被害が起きている。
最近は夏でもシカが牛と一緒に草を食べているのを牧場主が確認している。今後、山野草グループとの情報交換や夏期の山岳地域や市街地の調査も行っていきたいとの発表でした。
● 三窪高原のレンゲツツジ生育地の保護活動
平成15年から17年にかけてシカによる食害が拡大してしまい、平成19年になって2か所、20年に3か所、21年に2か所、県の補助金を受けて防護柵を設置した。
育てている実生苗を数年後には植樹できるようにしたいとの発表でした。
後で行われた質疑にもありましたが、東京都が水源地の保護対策に先行着手した結果、東京都のシカ問題が山梨県や埼玉県に移行したといった経緯も見られることから、シカ対策は行政区域をまたがった広域活動として、連携していかなければならない問題だということです。
講演「シカが植物群落に及ぼす影響:草原への影響は複雑」
各地の活動事例の後、休憩を挟んで、スペシャルゲストの麻布大学獣医学部教授の高槻成紀さんのお話がありました。動物生態学が専門で、「シカの生態誌」「野生動物と共存できるか」といった著書があります。
この日のお話の内容をメモ書きしたものを記載しておくと、
6月に生まれたメス鹿は、翌年の秋には妊娠が可能となり、その翌年、つまり生まれて2年後には子供を産むことになり、ほぼ毎年子供を産み続ける
一夫多妻のオス鹿は、初秋までに増えた体重が20kg減量するほど交尾に励む
大寒波の年、春の大雪などで頭数が半減するほど大量死しても、すぐに頭数は回復する
冬場はササを食べるが、枯れ葉も食べる
ブナ林のスズタケが食べられてしまった後にはツツジ科の毒草が繁茂していた
シカのいる林では幼樹が少ない
ススキの草原に柵を設置しそのままにすればやがて林に変わること、シカにより草原が維持されているという見方もできる
植物は食べられっぱなしではない、トゲのあるもの、シカのきらいな臭いを放つもの、有毒な成分をもつもの、固くて食べにくいもものがあり、また、ササは食べられた分だけ新芽の数が増える
シカの採食影響は、個々の種だけをとらえるのでなく、群落としてとらえる必要がある
自然保護も種の保護から生態系機能の保全へと変わってきている
野生動物の研究に携わってきて、いろんな生き物がつながって生きていることの素晴らしさを感じており、シカ問題をはじめ、個々の問題としてではなくバランスの問題としてとらえ、どういう自然を考えるのか、ビジョンをもって取り組んでいく必要があるといったお話でした。
フォーラムに参加しての考察
三ツ峠ネットワークも、単にアツモリソウを保護するだけでなく、生育環境を保全するという考えで取り組んでいますので、そのためにはコドラート調査をして、継続的に観測していくことが重要です。
シカを害獣として補殺するのではなく、シカを狩猟していくことは日本人の生活文化の問題として、取り組んでいかなければならないということです。そのためには、行政・林業・猟友会・市民のコンセンサスが得られるよう、地域文化のビジョン作りを話し合っていく必要があるでしょう。
ユキちゃんを役場に届け出しました
三ツ峠山荘の子犬ユキちゃんも事務局に来てから1か月たち、この1月8日をもって生後3カ月になりましたので、役場に畜犬登録をして鑑札をもらってきました。
事務局のベランダでくつろぐユキちゃん

近くの空き地で孫娘と走り回るユキちゃん

マツについて調べてみました(続)―菌根菌との共生関係
マツと菌根菌の共生について
マツの吸収根のほとんどは菌類と菌根を作り共生しています。菌根を形成する菌根菌の力を借りて、マツは荒れ地でも生育できることから、先駆植物(パイオニアプランツ)とも言われています。
火山噴火のような荒れ地では、マツ類の種子が飛来し発芽しても、生育できないで終わることも多いようですが、何らかの作用で菌根菌と出会うと、突如急激に成長を始め、やがて菌根菌のきのこも発生してくるようになります。
しかし土砂崩れや山火事程度の荒れ地では、菌根菌が無くなってしまうことはないため、発芽後まもなく菌根菌とであうことができ、回復は早いようです。
しかし、マツは陽あたりがよくないと生育できない陽樹であり、いったんマツ林ができあがってしまうと幼樹が育つことができなくなります。代わりに日陰でも成長できる陰樹が成長してくるため、マツ林として世代を繰り返すことは難しく、やがて陰樹の林に遷移します。
天然のクロマツ林は海岸の断崖などに見られることが多く、天然のアカマツ林が残るのは尾根筋などで、他の樹種が侵入できない劣悪な環境の場所に限られています。
地上に有機物の蓄積が進み土壌が肥沃化すると、マツと共生する菌根菌以外の菌類が増え、土壌病原菌の密度も荒れ地より高くなりやすく、マツと共生する菌根菌は勢力が衰えてきのこも発生しなくなり、マツもまた弱体化すると考えられています。
逆に土壌が貧栄養なままであればマツの菌根も勢力を維持でき、マツの競争相手も現れることが難しいため、マツ林が継続することになると考えられています。
通常は落葉などが蓄積し草本や灌木が生えて土壌は肥沃化してきますが、それを阻止してきたのが人間の営みです。
かつて燃料などにするするため松葉掻きや柴刈りをしていたことが、土壌に有機物が蓄積することを妨げ、結果として土壌環境をマツと菌根菌に適した貧栄養な状態に維持してきたようです。
乾燥や貧栄養といった劣悪な環境に対しては強力なマツと菌根菌の共生関係も、土壌の富栄養化の前には無力で、人里近くのマツ林は、マツと菌根菌、それに人間を含めた三者の共生関係にあるといえそうです。
外生菌根菌についての補足です
マツと共生する菌根菌は外生菌根菌といわれ、きのこを形成するものが多く、アカマツでは数十種類、カラマツでも十種類以上のきのこが知られていて、中でもマツタケは有名ですが、マツタケはアカマツ以外にもツガやコメツガなどにも菌根を作るようです。
外生菌根菌は種類が多く、主に樹木の根と共生し、樹木が光合成によって生成した糖分を根からもらう代わりに、根の養分吸収や水分吸収を促進し、根の耐病性を向上させ、さらには土壌中のアルミニウムイオンや重金属イオンなどの有毒物質から保護するといった働きをしているそうです。
従って肥料分の少ない土壌においては、菌根菌の接種によって樹木の生長は大きく促進されます。ただし肥沃な土地ではこの機能は目立ちません。また菌根化することによって土壌病原菌に対して抵抗力が大きく向上することになります。
植物の肥料要素は無機化されてから植物に吸収されると考えられてきましたが、菌根菌の菌糸は無機化したものを吸収するだけでなく、ときには有機態のまま吸収して樹木に供給するということがわかってきたり、菌根菌の菌糸が有機酸で積極的に岩石を溶かして、リンなどの元素を吸収していることも明らかになってきているそうです。
ラン型菌根菌も調べてみました
ラン科植物と共生するラン型菌根菌は、他のタイプの菌根を形成するものとは大きく異なり、単独で腐生的に生活する能力を持つものがたくさんあります。
ラン型菌根菌は、ラン科植物の吸収根の皮層細胞内に菌糸コイルを形成しますが、一定期間を経ると植物に分解吸収されてしまいます。
また、外生菌根菌の一部には、樹木と外生菌根を作る一方で、ラン科植物ともラン型菌根を形成するものがあります。ラン科植物の多くは生活に要するエネルギーの一部または全部を菌根菌に依存するため、全体としてみると樹木が菌を介してそれらの植物を養っていることになります。
葉緑素を持たず光合成を行うことのできない無葉緑ランは、腐生ランとも呼ばれますが、菌根菌に寄生している菌従属栄養植物です。
三ツ峠のカモメラン 三ツ峠のヒメムヨウラン
三ツ峠のヒメムヨウラン
ラン科植物の種子は微細で、未分化な胚があるだけで、胚乳はなく、自然下ではラン型菌根菌が存在して初めて発芽が可能になります。吸水した種子に菌根菌が侵入し、外から養分を運び込むことによって胚の分化が始まり、菌類との複合体を形成することで、ラン型菌根をもった植物体へと成長します。
ランの種類にもよりますが、糖などを含んだ培地に播種して無菌的に発芽させることが、園芸分野で行われています。ラン科植物単体を育てることができても、自然下での生態系が再現できているのではありません。造花を楽しむのとなんら変わらないと思います。
希少植物を保全していくために研究することはよいとしても、園芸的に栽培し売買することは奇をてらった金儲けにすぎず、ひいては天然ものはより貴重で高価に取引できるということにつながり、再び自生地が盗掘の被害に遭うといった危険性があります。
山野草を売買する人たちが、山野草を通して自然界の美しさや不思議さを観賞したり自然環境を理解する心から、一番かけ離れているように思えます。
マツについて調べてみました(続)―フィールド知識
富士山北麓のマツ科植物について
富士山には亜高山帯で見られるハイマツが見られません。富士山が独立峰で、南アルプスや八ヶ岳・奥秩父の亜高山帯から遠く離れているため、そこのハイマツ帯に棲むホシガラスの貯食行動圏外となっているからでしょうか。
ヒメコマツは一合目の青木ヶ原樹海から五合目までの針葉樹林内に点在していて、樹海では、直径が1m近く、高さが20mを超えるような個体を見ることがあり、リスなどが好んで食べています。
五合目で見られるのは稚樹で、小さいながら球果を付けているのを見かけることもありますが、あまり多くは見られません。リスたちが長い年月をかけて、麓から順次植樹(?)しながら登山していって、とうとう森林限界までたどりついたと言えます。
富士北麓の登山道を一合目から五合目まで登っていくと、マツ科植物が標高によって棲み分けているのがわかります。標高が高くなると、ツガ属はツガからコメツガに、モミ属はウラジロモミからシラビソに変わります。オオシラビソは日本海側に多いといわれていますが、富士山北麓では、シラビソと一緒にオオシラビソも見られます。
溶岩流上のマツ科植物
北西部の青木ヶ原溶岩流の樹海は、ツガやヒノキが中心の原始林で、アカマツ、ヒメコマツ、ハリモミなども混生しています。
北部のスバルライン沿いの剣丸尾溶岩流上にはアカマツ林が、そして東北部の山中湖村の鷹丸尾溶岩流上には国の天然記念物に指定されているハリモミ純林があります。中に入ってみたことはありませんが、道路から覗いて見るとアカマツとハリモミが混生していて、ハリモミの幼樹も見かけますが、モミの幼樹が多く見られます。
山中湖村のアカマツとハリモミ
山梨日日新聞2010年7月21日付けの記事「ハリモミ人工育成順調 山中湖―古里の純林再生目指す」によると、山梨大学の先生が中心になって10年ほど前に種子を発芽させ、育てた苗木5千本が、3年前県に寄贈され県有林に植樹されているものが順調に生育しており、ゆくゆくはハリモミ純林の再生につなげる計画のようです。
三ツ峠山のマツ科植物
三ツ峠山の河口登山道沿いはカラマツとウラジロモミが中心で、尾根筋や岩場の日当たりのよい場所にはアカマツが混生しています。登山口あたりではツガを見かけ、そして登山道途中ではヒノキが育ってきているところがあり、シラビソも混じっています。
また三ツ峠山荘の南東斜面では、葉のとがったトウヒ属の仲間を見かけます。イラモミ(マツハダ)だと思いますが、どうでしょうか。

マツについて調べてみました
マツ科植物について
マツ科植物は北半球の温帯地方を中心に分布し、針葉樹の半分以上がマツ科植物の種類です。南半球には本来分布せず、現在南半球にあるのは北半球から移植したものです。
日本に自生するマツ科植物は、マツ属・モミ属・ツガ属・トウヒ属・トガサワラ属・カラマツ属です。カラマツ属は黄葉して落葉しますが、他は常緑樹です。日本に自生していない公園や街路などで見られるヒマラヤスギは、同じマツ科のヒマラヤスギ属です。
日本のマツ属は、大きくは二葉松(ニヨウマツ)と五葉松(ゴヨウマツ)に分けられます。アメリカや中国・ヒマラヤには三葉松(サンヨウマツ)もあります。
日本に分布する二葉松類は、アカマツ・クロマツ・リュウキュウマツがあります。
海岸で多く見られるクロマツは、黒っぽい木皮で力強い二枚葉を持ち、男松と呼ばれ、里山や山の尾根筋で多く見られるアカマツは、赤っぽい木皮で柔軟な二枚葉を持ち、女松と呼ばれます。
日本に自生する五葉松類は、ゴヨウマツ(ヒメコマツ) ・キタゴヨウ(ヒダカゴヨウ)・ヤクタネゴヨウ・チョウセンゴヨウ・ハイマツがあります。
ゴヨウマツの枝先
松かさと種子について
松かさの成長は、マツ属とヒマラヤスギ属は2年型で、他は1年型です。
アカマツやクロマツは、4~5月に開花して受粉が行われます。マツは風媒花で、雄花の花粉は風に運ばれやすいように2つの空気袋(気のう)を持っています。
雌花は、開花時に鱗片が開いていて、受粉するとかたく閉じます。受粉後に花粉はその年いったん休眠し、ひと冬越した翌春の6月頃に受精が行われると、胚が成長して、秋に成熟した種子となります。
種子の成熟に2年かかるので、マツの枝を観察すると、雌花は新芽の先端に、雄花は新芽の下部につきます。新芽の根元、つまり昨年の枝先に昨年から成長した未熟な松かさがあります。更にその下の方には種子を放出した後の松かさがついていたりします。
種子が成熟すると松かさの鱗片が反り返り、種子はすき間から落ちて風に乗って散らばります。種子を放出した松かさはやがて地上に落ちます。
クロマツやアカマツの種子には翼があり風によって分散するため、実は小さくて食用には適していません。
ヒメコマツには種子とほぼ同じ長さの翼がありますが、ハイマツや、チョウセンゴヨウの種子には翼がなく、貯食行動を示す動物によって松かさごと運ばれ、食べ残された種子が親木から離れた場所で発芽します。ハイマツはホシガラス、ヒメコマツやチョウセンゴヨウはリスなどにより散布されます。
食用にされる「松の実」は、種子が大きいチョウセンゴヨウの実で、八ヶ岳や乗鞍岳などに自生しているようです。
松の実にはタンパク質が豊富で、オレイン酸やリノレン酸、それにマグネシウムや亜鉛が多く含まれ、中国では「長生果」と呼ばれていて、仙人の霊薬で、不老長寿の薬として、また滋養強壮薬として利用されています。
古い薬物書に、松の実を粉にして卵大の団子にしたのものを、1日3回酒とともに食べると、百日で病は治り、三百日で1日500里歩けるようになり、もっと長く服用すると仙人にさえなれるとあるそうです。
日本の山伏も山での修業時にマツの実や葉を食したといわれていますが、卓越した脚力を身につけたのもマツのパワーのお陰でしょうか。
モミ属、ツガ属、トウヒ属の見分け方について
モミ属とトウヒ属の樹形はクリスマスツリー型で対称であるが、ツガ属の樹形は頂部が斜めに傾いていて非対称である。
モミ属の松かさは直立し、種子が熟すと鱗片がはがれ落ちて軸だけ残っている。ツガ属とトウヒ属の松かさは下垂し、種子が熟すと鱗片が開いて隙間ができる。ツガ属の松かさは小さく、トウヒ属は大きくて長い。
富士山御庭のシラビソ
 富士山奥庭のコメツガ
富士山奥庭のコメツガ

モミ属の葉柄部は吸盤状になっていて、葉が落ちると枝に円形の葉痕が残る。ツガ属は葉のつく枝の部分が盛り上がって葉枕を形成する。トウヒ属ではこの葉枕部分が発達して突き出ている。
モミ属のモミの当年枝には毛があるが、ウラジロモミには毛がなく、縦しわがあり、シラビソやオオシラビソには細毛があって、縦しわがない。シラビソとオオシラビソの違いは、当年枝を上から見たときにシラビソは枝が見えるが、オオシラビソは葉に隠れて見えないという。
モミとウラジロモミの樹皮はツガ属やトウヒ属と同様に鱗片状にはがれるが、シラビソとオオシラビソは平滑で樹脂袋が点在する。
ツガ属のツガの当年枝には毛がないが、コメツガには毛がある。ツガの葉柄はほぼ直角に曲がるが、コメツガはそれほど曲がらない。
トウヒ属のトウヒの樹皮は灰白色で鱗片は小さめ、他は灰褐色でヤツガタケトウヒ(ヒメマツハダを含む)の鱗片は小さめだが、ハリモミ(バラモミ)、イラモミ(マツハダ)、ヒメバラモミは灰褐色で鱗片は厚めで大きい。
トウヒの葉は扁平で表面に2条の灰白色の気孔線があり、他は菱形で4面に気孔線がある。イラモミはやや扁平で弓なりに上向きにねているが、ヤツガタケトウヒは開出している。ハリモミの葉は太めで15~20mmと長く先が鋭くとがっているが、ヒメバラモミは10~13mmと短い。
トウヒ、ヒメバラモミの松かさは長さ3~6cmと小さめで、イラモミ、ヤツガタケトウヒ、ハリモミは6~12cmと大きい。
参考までに調べた事項を整理して列挙してみましたが、環境条件などによって形や大きさ、色など一概にはいえませんので、やはりフィールドに出て観察してまた調べてと、何回も繰り返さないと見分ける力はつかないでしょうね。
新年のご挨拶を申し上げます
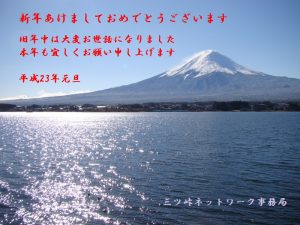
お正月といえば普通は元旦からの三が日ですが、松の内のことをお正月ともいいますよね。お正月飾りを松飾りということから、これを飾っている期間が松の内で、もともとは小正月(1月14、15日)までだったのが、今では1月7日に短縮されている地域が多いようです。
お正月に松を飾るのは、年神を家に迎え入れるための依り代という意味合いで、平安時代から新年に松を家に持ち帰る習慣が始まっていて、室町時代には現在のように玄関の飾りとするようになったそうです。
平安時代から常緑樹で長寿の松はおめでたいものとされ、その後室町時代には節目正しく真っ直ぐ伸びる竹が縁起のいいものとされ、さらに江戸時代になって春先に花を咲かす梅も加わって、「松竹梅」が縁起のいいおめでたいものとなったといわれています。
正月飾りや古いお札・お守りなどは神社に持っていって焼いてもらいますが、山梨県では道祖神祭りとの結びつきで、現在でも「どんど焼き」の風習が残っていて、1月14日の夜に、道祖神場で松飾りなどを焼く地域が多くあります。
このどんど焼きでは「まゆ玉団子」を焼いて食べる習わしです。かって農民の現金収入を支えたのが養蚕で、今はモモやブドウなど果樹の主産地である山梨県も、かっては稲作と合わせて養蚕が栄えていました。小正月に蚕の繭の形をした団子を作って飾り、これを焼いて食べる風習は、養蚕繁栄の祈願の意味があったようですが、子供たちにこれを食べさせ病気にならないように願ったことや、地域によっては、子宝に恵まれるようにと新婚さんをお祝いする所もあったようです。
ところで、三ツ峠山荘に猫の絵の描かれた大山祗命の護符が祀ってあるのをご存知ですか。昨年中村さんから同じものをいただき、三ツ峠ネットワーク事務局にも貼ってありますが、三ツ峠山の南東側登山口である西桂町の山祗神社の護符です。
毎年5月5日には、この護符を持って氏子が三ツ峠山に登り、権現尾根にある神鈴権現にお祈りしてくるそうです。大山祗命は山の神ですから、三ツ峠山を神として崇めた護符だと思いますが、猫が描かれているのはかっての養蚕との関連でしょうか。お蚕を食べる鼠を猫が捕ってくれるのを願ったものだという説もありますがどうでしょう。
皆さんはお正月の初詣にお出かけですか。事務局の裏手に熊野三大権現を祀った社がありますので、そこで三ツ峠ネットワークの活動が皆さんのご支援・ご協力で充実したものとなるよう祈願してきました。今年も宜しくお願いします。
新年会のお知らせ
新年1月15日に、三ツ峠山荘にて「三ツ峠ネットワーク新年会」を開催します。新しい年の活動について話し合いたいと思います。ご都合をつけてご参加ください。
集合は15時、会費は一泊二食7500円
夕食前に活動についての話し合いをします。夕食時の乾杯用のお酒は会費に含まれています。夕食以降はそのまま懇親会となりますが、持ち寄りとしますので、たくさん飲み食いしたい方は自前でご持参ください。大勢のご参加をお願いします。
参加される方は、三ツ峠山荘もしくは三ツ峠ネットワーク事務局までご連絡ください。
今年の活動を振り返って―続き
今年も明日はいよいよ大晦日です。今年の三ツ峠ネットワークの活動を総括する上で、三ツ峠山荘の中村光吉氏が、 去る11月30日、東京都新宿区霞ヶ丘町の「日本青年館」で開催された「山はみんなの宝!全国大会」―山の自然保護と適正利用を考える“国民会議”立上げのために―において、「山の植生保護―高山植物の盗掘、踏みつけとシカの食害、及びニホンジカの増えたことについての考察」を講演されていて、その内容について語り合ったことを紹介しておきたいと思います。
盗掘、踏みつけとシカの食害
三ツ峠山は多様な生態系を呈し、絶滅危惧種である希少動植物種アツモリソウが自生していて、かっては登山道わきにたくさん見られたと聞きますが、盗掘や踏みつけによって生態系のバランスがくずれ、株数が減少するとともにササやテンニンソウ、それにヤマドリゼンマイといったアツモリソウにとっての脅威植物がはびこるエリアが広がってきてしまっています。
これまでのように監視パトロールだけではアツモリソウを保護できなくなり、アツモリソウにとっての植生を復元するため、行政や地権者の許可をもらい、これらの脅威植物を除去するなどの作業をボランティア仲間と一緒に行うようにしています。
また、カラマツの根元近くにアツモリソウが残っていたりしますが、これはあまり目立たず盗掘や踏みつけなどの被害に遭わずにすんだからで、それが今やカラマツの成長によって日光が当たらなくなり、今はアツモリソウの生育の障害になってしまっていますので、大きく成長したカラマツの下枝の除伐作業も行っています。
一緒にアツモリソウの保護活動をするボランティア仲間でネットワークを結成するに至ったところに、今年になってニホンジカの採食影響が生じました。これまでもニホンジカをたまに見かけることはありましたが、カモシカもいたりして、食害問題までには至っていませんでした。
今年の4月にカモシカをセンサーカメラで撮ってありました。
雪が残っている4月18日の写真
 雪が溶けた後の4月23日の写真
雪が溶けた後の4月23日の写真

ニホンジカが群れで来るようになったからだと思いますが、今までよく見かけたカモシカが見られなくなりました。どこか別の場所に追いやられてしまったようです。
ニホンジカの食害問題は三ツ峠山だけでなく、高山植物の豊富な南アルプスなどのお花畑でも深刻な状態にあり、それらの地域で活動されているグループに教えてもらいながら、お互いに連携し合って活動していきたいと思います。
ニホンジカが増えたことについての考察
ニホンジカが増えたことを考えてみると、一つに牧草地が原因となっているように思います。ニホンジカはカモシカとちがって本来は移動性の生活をしてきました。一か所食いあさってダメージを与えても、翌日以降は移動して同じ所にはしばらく戻って来ないので、植生も復元する機会があります。カモシカは自分のナワバリで採食するため、食いあさることなくツマミ食いのような食べ方をするので、ダメージもほとんど与えません。
ところが山麓に牧草地が拡大したことで、昼は牛が放牧されていても夜は牛舎に入ってしまい、ニホンジカが牧草を採食するのは容易です。周辺にはスギ林などが植林されていて隠れる場所もあります。さらに最近は休耕地も増えていますので、牧草地と相まってニホンジカを定住化させてしまっているのではないでしょうか。
牧草は山野草と違って栄養も豊富であり、繁殖活動も旺盛になっているようです。いっそのこと牧草地を昼は牛を放牧し、夜はニホンジカの自然牧場として、人の管理のもとで鹿牧場を作ることを考えてみたらどうでしょうか。
ニホンジカが増えたもう一つの原因として林道の問題があるように思います。野生動物は本来自分たちの獣道を使って移動していましたが、これだけ林道が増えてしまい、しかも通常は使われず夜であれば全く使われないことから、夜行性の野生動物にとって便利な高速道路になっているといった印象です。採食や交尾のための行動範囲が広がったということが考えられます。
晩秋になって夜間は山頂付近で雄ジカの交尾期の鳴き声が聞こえていましたが、この時期再びヒロハツリバナが採食によって新たに皮剥ぎ状態になっているのが見つかりました。単に草の代用に木の皮を食べているとは思えません。
========================================
宮下正次著「炭はいのちも救う」という本に次のような記述があります。
栃木県・足尾の山では「森林の会」などが炭を撒き、マツを元気にさせてきた。ところがあるとき、土壌表面に一面に撒いた炭がなくなっていた。どうしたのかと首をひねっていたところ、シカの糞が黒光りしていることに気がついた。シカが食べたのかもしれないということで、今度はシカが食べやすいように一袋分を山盛りにして、塩をふりかけて置いてきた。数ヵ月後に現地に入ってみると、そこには炭がひとかけらも残っていなかった。・・・シカはミネラルの補給のために炭を欲していたのではないだろうか。
草の生える土壌の表面ではミネラルが乏しくなっていて、いくら草を食べても、シカはミネラル不足になっていたと考えられる。それどころかミネラル不足の草すら生えにくくなっているので、樹木へのシカの食害はますます増えることになる。土壌に十分なミネラルを補給して豊かな土壌を作ってやれば、ミネラルをたっぷり取り込んだおいしい草ができ、シカも落ち着いてくるだろう。
========================================
幹をプラスチック製メッシュで胴巻きしてニホンジカによる皮剥ぎ被害を防いでいる事例もありますので、林のヒロハツリバナに同様の対策をとり、試みに周辺に塩をふりかけた炭を撒いてみようかとも考えています。
これらのことは、ニホンジカだけでなくクマやイノシシの問題とも相通じるところがあるように思います。人間の都合でやってきたことが、知らず知らずのうちに野生動物の生態系を狂わせてきたのではないでしょうか。人間が自然を利用する上で、野生動物との折り合いをつけるための施策が必要な時期だと暗示してくれているように感じます。
「山はみんなの宝!全国大会」の趣旨である「山の自然保護と適正利用」について、三ツ峠を拠点に一緒に活動していただける方は、「お問い合わせ」から三ツ峠ネットワーク事務局までご連絡ください。
