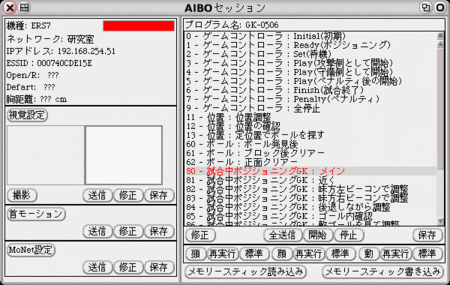先月とうとう106を売り払って新車を購入しました。予算は前回の半額以下で国産車ですが、いくつもの快適装備にびっくりしています。
もう思い出すこともないでしょうから、106を売った理由であるトラブルの数々を思い出せる限り書いておきます。
フルシーズン
エンジンがかからない。30分かからなかったことアリ。(購入3年目くらいから。これが買い替えの決め手)
荷室ランプがつきっぱなし。(オカマ掘られた後から。フレームゆがんだみたい)
外気導入ボタンを押すとカチカチ音がする。(3年目くらいから。部品交換後も発生。最近は回路をきってもらった)
ウインカーが必要以上にチカチカする。左折してウインカーが戻った後もチカチカがとまらない。(2年目、クレームで処理)
左テイルランプがサビてつかない。(オカマのせいで水が入った。交換費高かった)
クラッチがたまに戻らない。(2年目から。ダブルクラッチに慣れた)
夏期
エアコンが効かない。エアを詰め替えたが空気が入ってしまうらしい。(最近)
エンジンの回転数が上下する。アクセル踏むとエンストする。(2年目、クレームで処理)
オーバーヒート。(最近。冷却水が減ったため。何で?)
冬期
助手席ドア閉まらない。閉めるとバーンとはねかえってくる。(5年目くらいから。面白い。無視)
助手席ドア開かない。内側も外側もレバーを引いてドアが開かない。(同上。結構アセる)
運転席ドア閉まらない。必ず半ドアになる。(最近。外から押せばヨシ)
いろいろとトラブルがあり修理費も総額(オカマ別)で100万を越えたと思いますが、エンジンのかかり以外は全て許せました。今まで乗った7台の車の中でも一番気に入っています。(動いた後の)エンジンとハンドリング、身の軽さは本当に素晴らしかったです。